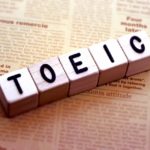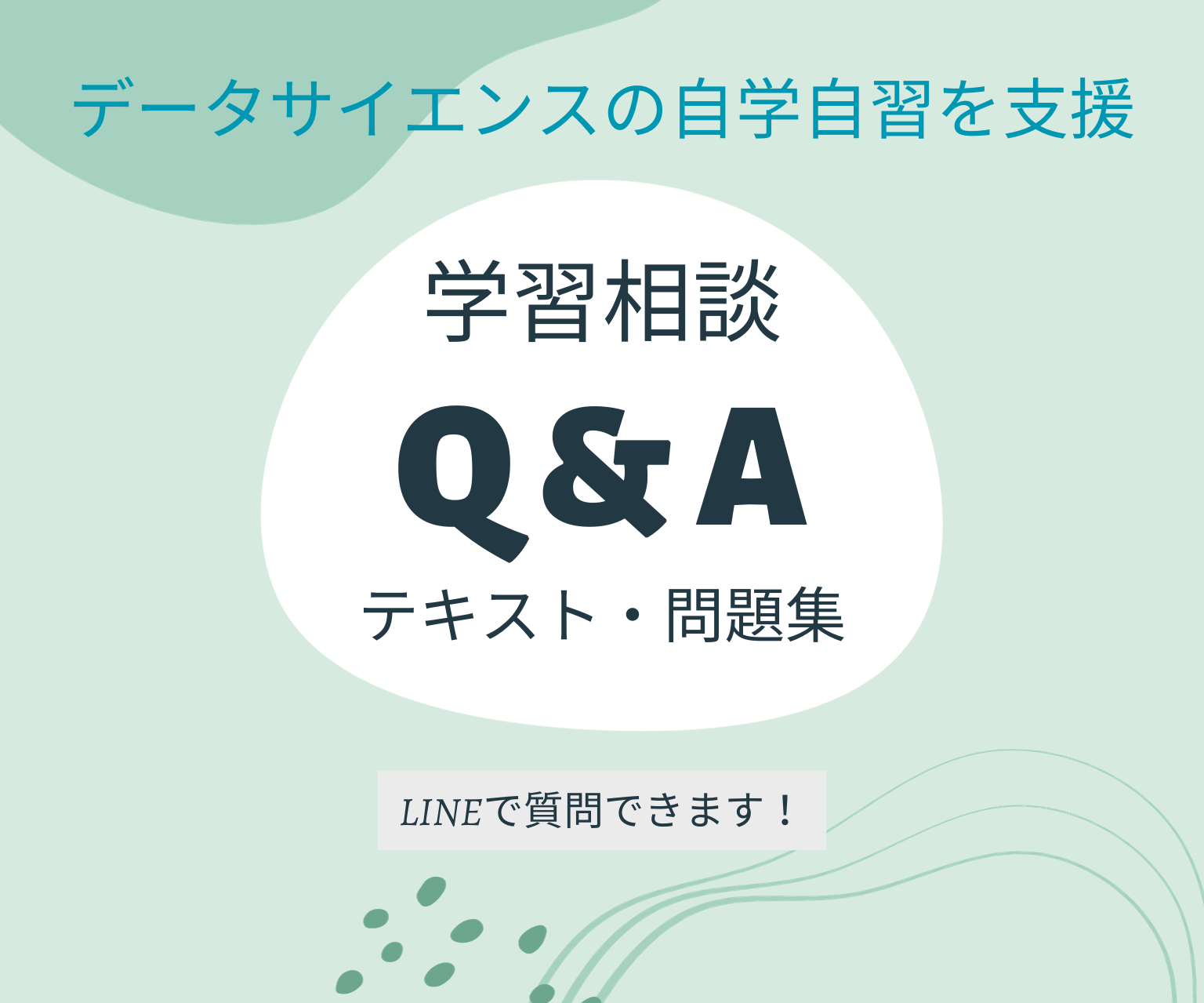ライターとして文章を書くことを生業にしている手前、色々な方から文章に関するお悩みが寄せられますが、その中でも「文章を書いている途中で迷子になってしまう」「時間をかけず文章を書けるようになりたい」というのは非常に多い相談事です。
その解決策のひとつとして、文章に取り掛かる前に「プロット」をきちんと練り上げるべきという点については別記事プロライターが教えるライティングのコツ①「プロット編」でお話しました。今回はプロライターが教えるライティングのコツ②「執筆編」に引き続き、文章のクオリティを底上げする「推敲(すいこう)」のコツをお伝えします。
推敲、校正、校閲の違い

「推敲」とよく似た言葉に「校正」と「校閲」がありますが、「推敲」についてお話する前に、まずはこれらの違いについて先にお伝えしておきます。
推敲:詩や文章を作る際に、字句や表現を何度も練り直すこと
校正:元の原稿と照らし合わせて、作成中のコンテンツに誤植や、色彩の違いなどがないかを確認すること。誤字脱字などのミスの発見、修正も含まれる
校閲:誤記はもちろん、表記の揺れ、事実関係の誤り、差別表現や不快表現などの不適切表現の有無まで、幅広くチェックし訂正すること。コンテンツ内の論理構成や内容に矛盾が起きていないかのチェックも含まれる
ざっくりと例示すると
「今皿ながら、2020年が閏年だったことに違和感があった」という文章に対して
・本当に2020年が閏年だったのかという事実関係を調べるのが「校閲」
・今皿→今更と修正するのが「校正」(校閲に含まれる場合もある)
・「違和感があった」か「違和感を覚えた」のどちらが適しているかを考えるのが「推敲」
というイメージです。内容に誤りがない、誤字脱字がない状態にするのが「校正」「校閲」ならば、文章のクオリティを底上げするのが「推敲」です。彫刻家の例でいえば、細部にこだわって作り込んでいく作業といえます。推敲の時間を設けることで、文章を執筆する際は多少荒削りでも進めていけるというセーフティーネット的な役割もあります。
プロライターが考える推敲のコツ

文章を推敲する際にはさまざまなポイントがありますが、その中で代表的なものをいくつかご紹介します。
一旦時間を置いてから読み直す

思いの丈をぶつけた文章が完成したら、少し時間を置いてから推敲することをおすすめします。文章が完成した直後は「やった!できた!」という高揚感に満たされ、アドレナリンが放出されている状況のため、細部のミスなどに気づきにくいです。冷却時間を置くことで自分の文章を客観的に見直すことができるため、まずは一旦その文章のことは放念しましょう。完全に忘れるほど放っておくのが理想ですが、〆切などとの兼ね合いもあると思いますので、少なくとも1日は間を開けることをおすすめします。
脳科学的にも、寝ている間に脳の司令塔「海馬」が断片的な情報や記憶を整理していることが明らかになっています。これらのことから、一晩寝かせることで最初は思いつかなかった表現を思いつくこともあります。
紙に印刷したものを読み返す
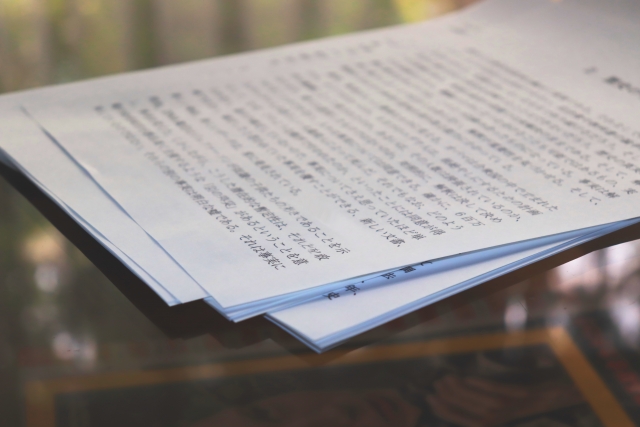
パソコンで文章を作成した場合には、紙に印刷をして見直すのもおすすめです。紙に印刷することで、客観的に文章を見ることができます。印刷したものを赤ペンで修正して見直すことで、自分の文章のクセなどにも気づきやすくなります。
文中の指示語に注意する

文章内に使いがちなのが「これ」「それ」などの指示語です。書いている最中は違和感なく使っているのですが、初見の読者にとっては「どれを指しているのか」がわかりにくいという状態にもなり得ます。特に取材記事などは「その時はそう思ったのですが」など、会話の流れで指示語が出てきやすいです。客観的に読んで分かりにくい文章の場合は、指示語ではなく元の単語を出すなどの配慮をしましょう。
主語と述語のねじれに気をつける

「ねじれ」とは、主語と述語が正しく対応していない状態のことです。例えば次のような文章を「ねじれ文」といいます。
「私の趣味は、料理を作ったり旅をします」
本来であれば「私の趣味は、料理を作ったり旅をしたりすることです」となるべきところ、「私の趣味」という主語に対し「します」という動詞が呼応しています。「そんな単純なミスはしない」と思うかもしれませんが、修飾部の多い複雑な文章になるとこれが発生するのです。
「私の趣味はいろいろな国の料理を作って友人達に食べてもらったりすることと、たまにそれらの国に旅をします」
これは文の構造が複雑すぎる時に起こりやすいため、2文に分けるなど簡潔な文章にするように心がけましょう。
文章は適度な長さに整える

「文章のねじれ」の話とも通じるものがありますが、1つの文章が長いと非常に読みにくく、論点も伝わりにくいです。自分で読み返してみて長いな、伝わりにくいなと思う文章があれば、積極的に短くするように心がけましょう。
「私の趣味はいろいろな国の料理を作って友人達に食べてもらったりすることと、たまにそれらの国に旅をします」
↓
「私の趣味はいろいろな国の料理を作って友人達に食べてもらったりすることと、たまにそれらの国に旅をすることです」
↓
「私の趣味はいろいろな国の料理を作って友人達に食べてもらったりすることです。たまにそれらの国に旅もします。」
↓
「私の趣味はいろいろな国の料理を手作りして友人達にふるまうことです。時にはそれらの国に旅をしたりもします」
話が論理的につながっているかに気を配る

これはプロットをきちんと書いていればあまり起こり得ないですが、文章全体を通してきちんと論理的な組み立てができているかをチェックしましょう。自分ではパートごとのつながりが分かっているけれども、読者にイマイチ伝わりにくいと思ったら「それゆえ」「しかし」「一方で」など、接続詞をうまく使って文章の構造を明らかにしましょう。
最後まで気を抜かずクオリティ高い文章作成を

推敲は文章をブラッシュアップできる最後のチャンスです。せっかく時間と労力をかけた文章であれば、よりよいものを目指したいもの。クオリティ高い文章を作成するためにも、推敲の時間は必ず設けることをおすすめします。